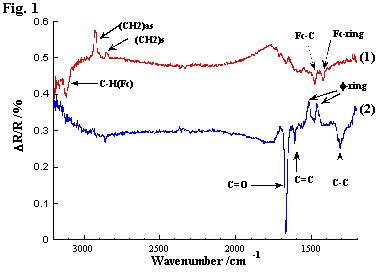
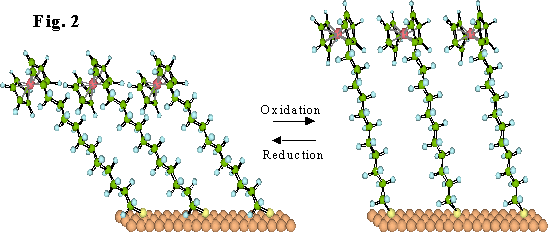
1.振動分光法とは?
人間の目で見える電磁波は、波長が380nm(紫色)から780nm (赤色)という電磁波の僅か一部分に過ぎない。電磁波を物質に当てたときの吸収と放出を測る事により、原子や分子内に起こる様々な過程について調べる事ができる。その中で、赤外光(波長が780 nmより長い光)は分子内の振動や回転のエネルギー準位に相当するので、その吸収に基づく測定法を振動分光法と呼ぶ。振動分光を行う方法として代表的なものに赤外光を当ててその吸収を見る赤外分光法と光の散乱をみるラマン分光法がある。これらの測定法は互いに相補的、つまり一方では見えないものが他方で見えるという関係にある。また、フーリエ変換赤外分光器の進歩やセル設計の改良などにより、赤外反射吸収分光法(IRRAS) や表面増強ラマン分光法(SERS)が電気化学系にも応用されるようになり、固/液界面における分子の振る舞いを単分子レベルで調べることが可能となった。
電子伝達体のフェロセン(Fc)、生体光合成に重要なポルフィリン(Por)やヒドロキノン(H2Q)やアゾベンゼン(?-N=N-?)などの機能性分子を、アルカンチオール分子に結合させ、自己組織化法(前の説明参照)により、金表面に単分子層として構築できる。特にこれらの官能基の電気化学反応にともなう単分子層の構造の変化を知る事は機能発現の機構を理解する上で不可欠である。
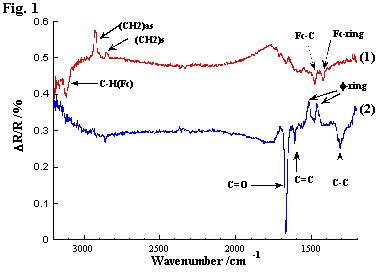
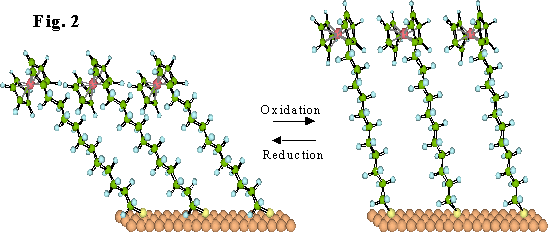
図1にFcとH2Qで終端化された(1)Fc(CH2)11SH (赤線)と(2)H2Q(CH2)11SH (藍線)の自己組織化単分子層のIRRASスペクトルを示したが、末端の官能基の酸化にともない、いくつかの赤外バンドが出現する事が分かる。(1)の場合、Fc環に帰属されるバンドのほかに、2850と2920cm-1にCH2基の対称(s)と非対称(as)の伸縮振動のバンドが観測された。詳しい解析によると、Fc(CH2)11SH単分子層のFc環が酸化されると、単分子層のアルキル鎖の配向が変化し、より電極表面に垂直するようになる(図2)。一方、(2)の場合では、H2Q/キノン(Q)による赤外バンドのみが観測され、3000~2800cm-1の領域にC-H伸縮のバンドは全く観測されなかった。即ち、H2Q/Q酸化還元反応に際して、図2に示されたようなアルキル鎖の配向の変化は起こらなかった。(1)と(2)の分子構造を比較すると、その違いは分子の末端にある官能基のみである。このように、官能基は分子構造、さらには酸化還元反応の速度に大きく影響を与える。
関連する論文:
(1) Ye, S. et al., Phys. Chem. Phys. Chem., 1, 3653-3659 (1999); (2) Ye, S. et al. Langmuir, 13, 3157-3161(1997); (3) Yu, et al. Langmuir. 16, 6948-6954 (2000); (4) Yu, H. et al. Langmuir, 14, 619-624 (1998); (5) Ye, S et al. J. Chem. Soc., Faraday Trans., 92, 3813-3822 (1996); (6) Sato, Y. et al. Langmuir, 12, 2726-2736 (1996); (7). Shimazu, K. et al. J. Electroanal. Chem., 375, 409-413 (1994).