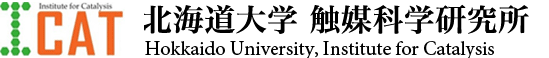令和3(2021)年度 北海道大学触媒科学研究所 共同利用・共同研究公募要項
触媒科学研究所(以下,本研究所という。)の前身である触媒化学研究センターは,平成22年4月から,触媒化学研究の共同利用・共同研究拠点として全国の研究者との共同利用研究を行い,触媒化学に関して多くの成果を生み出してきました。本研究所に改組するにあたり, 触媒化学の枠組みを大きく踏み越え,新しい触媒科学を構築するため,触媒基礎研究系,実用化推進系,ターゲット研究部に加え,新たに触媒連携研究センターを設置し,物理学,材料科学,生命科学,数学,情報科学,化学工学,などの異分野との融合を通して,深化した触媒科学に関する共同研究を進め,国際触媒研究ネットワークの形成を目指しております。
令和3(2021)年度も新しいエネルギー・資源・物質体系構築を目的としたサステナブル触媒の開発,触媒をコアとする新しい学術領域の創成,触媒機能の高度化や触媒の多次元解析支援などの共同利用・共同研究の実施することを予定しておりますので,下記の要領で応募願います。
記
1.公募区分
本研究所共同利用・共同研究は,本学外の研究者が研究代表者となり,本研究所の教員を研究分担者として本研究所において共同実施するもので,以下の公募区分があります。なお,公募区分(5)から(7)の公募要項については,下記に記載された箇所をご覧ください。
(1)戦略型:
研究者コミュニティの意見を踏まえ,本研究所が年度ごとに設定した共同利用・共同研究課題に基づき,研究計画の公募を行います。とくに,異分野融合ならびに国際共同研究を取り込む提案を歓迎します。
(別紙様式1WrodファイルPDFファイル
)
| 居室,研究環境の提供をはじめ,所要の物品購入や複数回の旅費等の支出が可能です。複数の研究機関(海外を含む)からの研究者の参画が可能です。年度当初から研究を開始し,年度を通して研究を実施します。(今年度の研究課題については,別表Ⅰ |
→詳細は,下記の要項2をご覧ください。
(2)提案型:
自由な発想に基づいた触媒科学分野に関連した研究課題及び研究計画の公募を行います。萌芽的な提案,触媒化学の枠を超えた提案などこれまでにない発想のものを歓迎します。
(別紙様式2WrodファイルPDFファイル
)
| 萌芽的,発案的,試験的,準備的研究の実施,研究会やワークショップの実施等,様々な共同利用・共同研究の形態を可能とし,その希望により機動的に開始できるものです。(年3回の公募時期を設定) |
→詳細は,下記の要項2をご覧ください。
(3)届出型:
自由な発想に基づいた当研究所の教職員との共同研究の公募を随時行います。当研究所は経費を負担しません。
(別紙様式5WrodファイルPDFファイル
)
→詳細は,下記の要項2をご覧ください。(4)触媒科学研究所コロキウム:
研究成果などを本研究所において紹介あるいは討論を希望する方を対象に,研究所が主催するコロキウムとして講演して頂きます。当研究所は経費を負担しません。(別紙様式6WrodファイルPDFファイル
)
→詳細は,下記の要項3をご覧ください。(5)客員研究員:
本研究所教員と継続的・組織的に協力して,共同利用・共同研究を進める意欲的な研究者を客員研究員として若干名募集いたします。本研究所予算配分基準に基づき,研究費及び旅費を配分いたします。
→詳細は,本研究所ホームページの客員研究員募集要項(http://www.cat.hokudai.ac.jp/employment.html)をご覧ください。(6)触媒高等実践研修プログラム:
課題意識をもった研究者に対して触媒の実践的教育の場を提供しています。実験に関わる経費は,予算の範囲内において本研究所が負担します。旅費は支給されません。
→詳細は,本研究所ホームページの触媒高等実践研修プログラム公募要項(http://www.cat.hokudai.ac.jp/koubo/koubo24/koubo20120516.html)をご覧ください。(7)若手情報発信型:
海外の著名な研究機関において研究成果の発表を希望する若手研究者を対象に,研究所が主催する情報発信型国際シンポジウムの招待講演枠を提供するとともに,渡航費の一部を補助しています。
→詳細は,触媒学会を通して告知される公募情報(http://www.shokubai.org/)をご覧ください。
2.戦略型,提案型,届出型
2−1 受入単位
共同利用・共同研究の受入単位は,各研究部門,ターゲット研究部のクラスター,および北大触媒アライアンスユニットとなり,関係受入教員が研究分担者となります。なお,申請に当たっては,受入希望教員と課題の設定及び研究計画について事前相談が必要です。研究部門・研究クラスター,および北大触媒アライアンスユニットの研究概要,教員への連絡先については,別表Ⅱ ![]() を参照願います。
を参照願います。
2−2 研究期間
戦略型については,2021年4月1日から2022年3月31日まで,提案型については,採択(年3回の公募)から2022年3月31日までの期間とします。なお,戦略型・提案型とも継続申請が可能ですが ,採否は年度ごとに審査によって決定します。また ,戦略型研究を継続して実施できる年数は2年を限度とします。
届出型については,承認から当該年度末までの期間とし,継続年限に制限はありません。
2−3 研究経費
戦略型,提案型については,共同利用・共同研究の経費は,予算の範囲内(下表参照)において本研究所が負担します。購入可能な物品は,申請課題の遂行上直接的に必要なものに限ります。原則,旅費は,本研究所へのものとし,申請書に記載のある研究代表者,所外の分担者及び研究協力者について支給できます。
届出型については,当研究所は経費を負担しません。
表1.戦略型および提案型の区分,研究期間,採択件数,配分研究費上限額,応募締切
| 戦略型 | 提案型 | |
|---|---|---|
| 区分 | 年度ごとに設定した課題に基づき公募し,年度を通し研究を実施する。 | 共同利用・共同研究の希望の発生に機敏に対応するため,年3回の公募を行う。 |
| 期間 | 2021年4月1日〜 2022年3月31日 | (第一期)2021年 4月1日〜2022年3月31日 (第二期)2021年 8月1日〜2022年3月31日 (第三期)2021年12月1日〜2022年3月31日 |
| 件数 | 3〜5件程度 | 15件程度 (但し,予算状況により変動する。) |
| 配分研究費 上限額 |
100万円以内 | 15万円程度 |
| 応募締切 | 2021年1月29日(金) | (第一期) 2021年1月 29日(金) (第二期) 2021年 6 月 18 日(金) (第三期) 2021年 10 月 22 日(金) |
2−4 申請資格
申請をする研究代表者は,国籍を問わず,学外の国公私立大学,公的研究機関及び民間企業に所属している研究者又はこれに準ずる研究者であると本研究所長が認めた者とし,海外の研究機関に所属する研究者も含まれます。
研究代表者は,当該研究を遂行するため,本研究所受入教員である研究分担者の外,上記資格を有する国内外の研究者を「研究分担者」として加えることができます。また,研究代表者が指導している大学院生(学部学生は除きます)を「研究協力者」として加え,研究を実施することができます。なお,分担者や協力者に加える場合には,事前に受け入れ教員の承諾を得てください。
2−5.申請方法
申請書(別紙様式1Wrodファイル![]() PDFファイル
PDFファイル ![]() (戦略型),別紙様式2Wrodファイル
(戦略型),別紙様式2Wrodファイル![]() PDFファイル
PDFファイル ![]() (提案型),別紙様式5Wrodファイル
(提案型),別紙様式5Wrodファイル![]() PDFファイル
PDFファイル ![]() (届出型))に必要事項を記入し,上記締切日までに提出願います。
(届出型))に必要事項を記入し,上記締切日までに提出願います。
なお,研究機関等に所属している方については,所属長の内諾を得たうえで申請してください(名誉教授等で,現在研究機関等に所属していない方を除く)。原則として,電子メール申請での受付となっております。申請書を添付し,メールの件名を【令和2(2020)年度共同利用・共同研究応募】と明記し提出願います。
戦略型と同一の研究課題で提案型に重複申請することができます。その場合は,申請書(別紙様式1Wrodファイル![]() PDFファイル
PDFファイル ![]() )の該当欄に○印を付記のうえ申請願います。
)の該当欄に○印を付記のうえ申請願います。
2−6.申請書提出期限
戦略型,提案型については,表1に記載の応募締切を厳守してください。届出型については,応募締切はありません。
2−7.選考
採否,採択額については,本研究所共同利用・共同研究拠点課題等審査専門委員会の議を経て,本研究所長が決定します。
2−8.採否の通知
戦略型,提案型については北海道大学北キャンパス合同事務部より,直接申請者へお知らせします。採択後,速やかに「共同利用・共同研究承諾書」(別紙様式3Wordファイル ![]() PDFファイル
PDFファイル ![]() )を提出していただきます。
)を提出していただきます。
届出型については受入教員より,直接,申請者へお知らせします。「共同利用・共同研究承諾書」の提出は不要です。
2−9.フェローの称号について
戦略型に採択された場合,原則として研究代表者に,「北海道大学触媒科学研究所共同研究フェロー」の称号を付与します。
2−10.共同利用・共同研究報告の提出,論文発表など
- 共同利用・共同研究報告書
共同研究実施期間終了後30日以内に,「共同利用・共同研究報告書」(別紙様式4Wordファイル PDFファイル
PDFファイル  ),およびA4版2頁(戦略型)又は1頁(提案型)で学会発表形式のレポートを提出願います。レポートは2022年3月末に本研究所ウェブサイトに掲載し,公開させていただく予定です。ただし,提案型の場合,成果を論文にて公表あるいは公表予定であれば,成果公表後に論文別刷りを送付することでレポートに代えることを認めます。 なお,届出型のレポートは任意ですが,上記提案型に準じたレポートの提出を希望します。
),およびA4版2頁(戦略型)又は1頁(提案型)で学会発表形式のレポートを提出願います。レポートは2022年3月末に本研究所ウェブサイトに掲載し,公開させていただく予定です。ただし,提案型の場合,成果を論文にて公表あるいは公表予定であれば,成果公表後に論文別刷りを送付することでレポートに代えることを認めます。 なお,届出型のレポートは任意ですが,上記提案型に準じたレポートの提出を希望します。 - 学会発表・論文発表
本共同利用・共同研究によって得た成果を学会や論文等で公表する場合は,本研究所の共同利用・共同研究で得られた成果である旨を謝辞として次のように要旨集や論文等に明記してください。発表後は,要旨集や論文のコピー等を速やかに本研究所の受入教員及び下記提出先に提出願います。
(和文)北海道大学触媒科学研究所共同利用・共同研究に基づき実施された(課題番号...)。
(英文)This study was supported by the Cooperative Research Program of Institute for Catalysis, Hokkaido University. (Proposal#.........)
また,北海道大学触媒科学研究所共同研究フェローの称号を付与された者は所属に「ICAT Fellow, Institute for Catalysis, Hokkaido University.」と明記ください。 - 知的財産権の取り扱いについて
本共同利用・共同研究によって生じた知的財産権の取扱いについては,別途協議するものとします。
3.触媒科学研究所コロキウム
3−1.受入単位
各研究部門およびターゲット研究部クラスターの教員が受入教員となります。なお,申請に当たっては,受入希望教員と事前相談が必要です。各研究部門・研究クラスターの研究概要,教員への連絡先については,別表Ⅱ
を参照願います。なお,北大触媒アライアンスユニットの教員は,コロキウム開催の受入教員には含まれませんのでご注意ください。
3−2.経費
原則,当研究所は経費を負担しません。
3−3.申請資格
国籍を問わず,学外の国公私立大学,公的研究機関及び民間企業に所属している研究者又はこれに準ずる研究者であると本研究所長が認めた者とし,海外の研究機関に所属する研究者も含まれます。
3−4.申請方法
4.提出先・お問い合わせ先
北海道大学北キャンパス合同事務部 研究協力担当
〒 001-0021 札幌市北区北21条西10丁目
TEL 011-706-9202,9264 FAX 011-706-9110
お問い合わせ先e-mail:k-kenkyo@jimu.hokudai.ac.jp
提出先e-mail:kyoten@cat.hokudai.ac.jp
URL:http://www.cat.hokudai.ac.jp